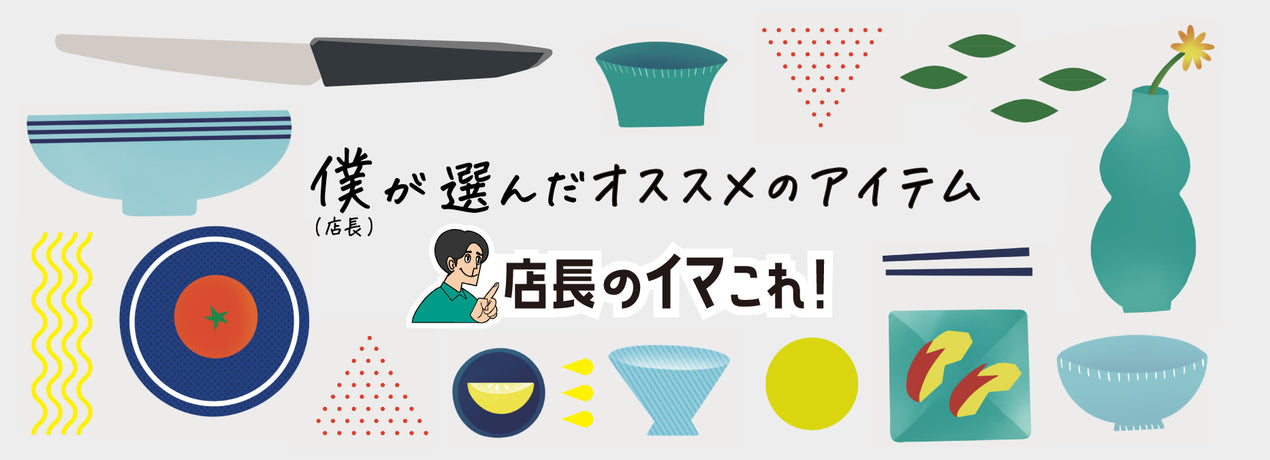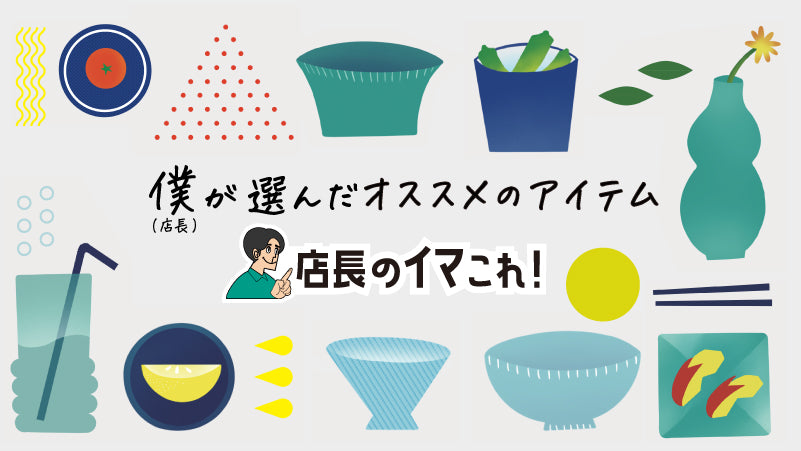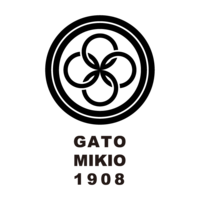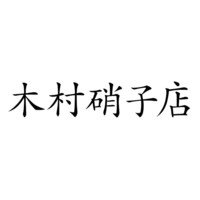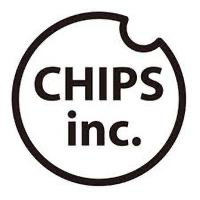-

新生活にはこれだ。休みの食べもの Vol.9
人は一朝一夕で変わるのは難しい。しかし暮らしは変えられる。案外モノで人の行動や意識は変わるのだ。それが生活雑貨の面白いところというものです。今は新生活シーズンも落ち着いてきたということで、新しい暮らしに慣れてきてちょっとした不便に気づきはじめる時期な人もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は新生活ドラフト会議と称して、ちょっと暮らしに取り入れてみたいなと気になっていたアイテムを実際に使ってみました。今回の登場人物 清水(筆者):狭小物件に住むデザイナー 小井沼:中くらいの物件に住むデザイナー 大倉:でかい物件に住む営業 好みが分かれる、まな板まな板は2種類を用意しました。2つ折りで開けば倍のサイズになるcutting matと、驚くほど軽い桐のまな板です。 ライトに使えるってのはどっちも共通してるね。そのなかで丁寧なくらし系か、便利寄りかみたいな。白い樹脂のまな板だと、見た目的にちょっとね 安っぽくは見えちゃうよね。一人暮らしを始めたての人には、ちょっといいものを買うことをおすすめしたい。 まな板ってそう買い替えるものじゃないもんね。うちのまな板10年以上つかってるもん。 薬味を机の上で切るとか、そのままテーブルに出してプレートとしてもつかえる お寿司…?たまごやきとか。四角ならではのたたずまいはあるよね。 黒でかっつり四角いってちゃんとして見える。カステラとか切んなきゃいけない系おやつにいいよね 大学生になって、一人暮らしはじめて買うなら、中サイズかなぁ〜 俺らが大学の頃、プラスチックでこんなかっこいいまな板なかったもんね なかった。あと、収納サイズの割に全然こぼれる気配がないのはいいね 調理スペースが許すなら、まな板はデカければデカいほどいいもん 基本的に木のまな板は、使用前に水でしっかり濡らす必要があるなど、慣れないとなかなか丁寧な暮らしポイントの高い(注:手間のかかるという意味)アイテム。その中にあって「桐」という素材はかなり扱いやすい部類に入ります。なんといっても軽い。同じ厚みのプラスチックと比べても、ずっと軽いのです。 あっ想像の10倍軽い、倍くらい厚みあっても全然重さが気にならないかもね。 切り心地を試してみよう。桐のほうがなんというか、包丁がはね返ってくるような感じはないかも。切り心地にこだわる人にはおすすめかな キムチとか刻むと色うつりが心配じゃない?赤く残りそう みんな気になるでしょう。やってみましょう おお、すごいね、水で濡らしてから使うととぜんぜん残らないんだ 桐って思ってたよりまな板として便利なんだよね。しかも乾きやすいんだよ cutting matの正方形はアウトドアにいいね、汚れた面を内側にたためば持ち帰りやすいし。買おうかな そうやって持つと聖歌隊みたいじゃん あの、たまに結婚式で歌う時のやつ わからないから口パクで乗り切っちゃうやつね 絶対便利、調理のできる器お次はそのまま火にかけられて、テーブルにも出せる「調理のできる器」。当店で発売以来人気の、pot dishとKOKURYUのお出まし。これを使って、小井沼さんには煮込みハンバーグを作っていただきます。...
-

今年は茶碗で「米映え」をねらってみよう。
毎年秋が近づいてくると儀式のように、シンプルなご飯のお供で新米を丁重にお迎えしている。「普段は炊飯器だけど、新米を買った最初のご飯は土鍋で炊く」「ご飯に合うおかずをお取り寄せして楽しんでいる」なんて声もあったり、さすが日本国民の主食だけあって新米をVIP待遇する家庭は意外と多いみたいだ。それなら今年は、いっそのこと新しい「米映え」茶碗を用意して新米をお迎えしてみよう。いろは茶碗白地に青い柄の茶碗は「これこそご飯茶碗」という感じがしてたまらない。よくある茶碗と比べてややすっきりしたフォルムと、気の利いたサイズ感が特徴のいろは茶碗には、日本の焼き物の美味しいところが詰まっている。波佐見焼いろは茶碗は長崎県、波佐見町を中心に生産される波佐見焼の茶碗。カタチはごくシンプルですっきり、石膏の型から作られることから歪みが少なく綺麗な造形で、他のいろんな器にも合わせやすい器用さが魅力。 呉須の絵付けいかにもらしい焼き物っぽさが無いカタチに表情を与えるこの絵付け。呉須という藍色の絵具で、職人が一つ一つ丁寧に筆を入れていく。シンプルで歪みの少ない形に対して、深い青の筆跡が唯一無二の個性を与えて完成する。美しいカタチに味わい深い青の化粧、庶民的な茶碗ながらその出立ちは何とも粋で、洗練されているのに飾らない雰囲気が秀逸な仕上がりだ。この茶碗にホカホカのご飯をこんもりよそうと「あー、日本人してるなぁ」なんて思えて、白いご飯を食べるのが妙に嬉しくなってしまう。いろは 茶碗 1,540円陶眞窯 4寸マカイ沖縄の焼き物「やちむん」には分厚くて少しぽってりしたものが多く、この4寸マカイもその例に漏れず、どことなくかわいい形をしている。ゆるやかな口先ほどのいろは茶碗と比べカーブが強く、口の部分はフワッと広がっている。このゆるやかな横顔が化けるのはご飯をよそう時、ドーム形に盛られた真っ白のご飯を柔らかく讃える口、この形が美しい。それに箸も入れやすく、ひたすらご飯にやさしい母性的な作りが魅力的な逸品だ。沖縄を感じる絵付け柔らかいアイボリーの上で優雅に広がる絵柄は、本州の焼き物にはない独特の雰囲気があり、沖縄のゆったりした空気の中、日に照らされた花を眺めているような気分にさせてくれる。そしてこの色彩と真っ白いご飯が生み出すコントラストが、お米をさらにおいしくしてくれる気がする。カタチと色合い、どんな角度からもやさしく美しく包み込んでくれる様は、まさに沖縄といった感じでたまらない。陶眞窯 4寸マカイ 茶碗 1,283円自分だけのお茶碗CRAFT STOREオリジナル IDentityのお茶碗は、その日その時の窯の状態で焼き上がる、偶然の表情が現れた器だ。一つずつ表情の出方がまったく違い、2つと同じ柄ができることはない。生成色とうぐいす色が淡くまざりあう様には、白米が映えるいかにも焼き物らしい素朴さがありながら、日本画のように美しくも映る。すっきりと立ち上がりる形は手を添えやすく、男性、女性、子どもと、誰でも使いやすい。お茶碗は家庭の中で唯一「自分専用」がある器だ。世に2つと生まれないアイデンティティを重ねてみるのも、器との面白い付き合い方かもしれない。IDentity 茶碗 1,467円しのぎの茶碗縞柄というのもなんとなく茶碗らしいくて良い雰囲気だ。しのぎの茶碗は岐阜県が誇る美濃焼『竹隆窯』で生まれる、小ぶりで持ちやすいサイズ感と温もりのある質感が特徴の一品。絵付けによる柄ではなく、職人がヘラやカンナで丁寧に表面を削ってラインをつくる、色の濃淡をつくり和食器にモダンな印象を与えてくれる。古くから伝わる技法を現代の食卓にいかしたデザインが、炊きたてご飯をさらに引きたててくれそうだ。しのぎの茶碗 1,650円Pヘリンボーン茶碗Pヘリンボーン 茶碗は、ツイードなどの「ヘリンボーン柄」を表面にあしらった変わり柄の茶碗。お椀型といえばたわんだ形が多いけれど、Pヘリンボーン 茶碗は膨らまないシュッと上に広がるフォルムが特徴的。膨らみのあるお茶碗のかわいらしい印象に比べて、Pヘリンボーン 茶碗はスタイリッシュな印象で、白の陶器のやわらかい風合いとヘリンボーン柄が全体の印象をかわいらしくまとめてくれている。この絶妙な濃淡と幾何学的な雰囲気で「米映え」を狙ってみるのも良いかもしれない。Pヘリンボーン 茶碗 1,540円 新米を楽しむ最終兵器 お米の美味しさを芯から追求するなら、もはや茶碗だけでは語れない。 炊飯器でも土鍋でもない、釜で炊いたご飯は最強の米料理だ。 とはいえお米を愛していても、釜まで買うとなるとなかなかハードルが高いがこれはすごい、一合炊きの飯釜である。 ご存知の方も多いであろう駅弁「峠の釜めし」の容器がこのkamaccoのルーツであり、製造を行っている益子焼の「つかもと」が、釜めしファンの要望に答えて生まれた逸品だ。 Kamaccoの大きな特徴は優れた「耐熱性」と「耐火性」。 炊き方はガスコンロの弱火に20分、火を消して15分蒸らすだけで、面倒な火加減や炊く時間のストレスもない。炊いたご飯が冷めたら、そのまま電子レンジで温められるという優れもの。 ご飯のおいしさを引き出す土釜本来の機能もしっかり備わっているから、お米の粒がしっかり立ち、ふっくらした炊き上がりが楽しめる。 少し長めに火にかければ、おまけにおこげまで作ってくれるから驚きだ。 蓋は本格的な二重構造、内蓋は炊く時の軽量カップとして、さらに外蓋は炊き上がった後の茶碗として使える無駄のなさも素晴らしい。 ロマンにあふれる飴色の土釜がなんとも味わい深く、お釜ご飯の美味しいところをまるっと叶えてしまう、米好きには夢のような存在だ。 土鍋(土釜)ご飯...
-

夜長は良いグラスと共に。お酒を美味しく楽しむアイテムたち
夜が長くなってきた季節。酒飲みの私にとっては、しっぽりお酒を楽しみたくなってくる季節です。ちょっといいお酒、いやいやふだんのお酒も、良いグラスで飲み方を変えるとずっと美味しく感じられるもの。今回はCRAFT STOREきってのお酒好きを自負する私が、実際に使った上で特におすすめしたいアイテムをあつめました。気軽で上質、丁度いいワイングラス木村硝子店の「チャオ 12ozホワイトワイン」は個人的に特に気に入っているアイテムの一つ。夜長とは言ったものの、早速お昼からよく冷えた白ワインを飲みたくなってしまいます。丸っこく可愛げのあるシルエット。ボウルがコンパクトで普段遣いによく、ワインの温度を唇で感じる極薄すぎない薄さ。なんとも気軽に使える「ちょうど良さ」があるのです。それでいて、職人による手吹きのハンドメイド。ステムに継ぎ目がなく、映り込みもきれいなハリは、自称グラスオタクとしても納得です。この品質でこの価格は正直他に思い当たらないかも。スペイン南部の街で、罪悪感なくお昼から白ワインを楽しんだ心地いい思い出が蘇るのは、その気軽な使い心地のせいかもしれない。チャオはイタリア語だけどチャオ 12ozホワイトワイン 3,630円赤ワインをさらに楽しむ、次の一脚当店では勝手に「チャオ」とは兄弟分のように紹介している、同じく木村硝子店の「ギャルソン 24ozブルゴーニュ」。ちょっとワンランク上に、リッチに赤ワインを楽しみたいグラス。赤白問わず使えるような「よくある形」のワイングラスから一歩進んで、より赤ワインを楽しむための次の一脚。ギャルソンは、ふくよかな赤ワインの香りを存分に楽しめる形にデザインされています。大きく膨らんだボウルから、すぼまった飲み口へと香りが流れ、口に運ぶたび華やかな香りが鼻を抜けていく感覚。そんなにワインに詳しくないし、美味しく飲めればいい。という方でもこのグラスは楽しんで頂けると思います。いつもの赤ワインでも、驚くほど変わりますから。ギャルソン 24ozブルゴーニュ 4,840円ビールの美味しさを引き出す。二重タンブラーは巷でよく見かけますが、磨き屋シンジケートの二重タンブラーはひと味違います。一昔前に世界を圧巻した、あの某音楽プレイヤーの背面の鏡面を覚えているでしょうか。仕上げていたのは新潟、燕三条の職人たちというのは有名な話。見た目の美しさもさることながら、持ったときの気持ちよさ。あまりにもつるつるで手にピタッと馴染む触りごこちは、口だけでなく、指や唇でもプレミアム感を味わえます。美味しいビールは温度も大事。二重構造だから気温や手の温度を伝えにくく、冷たさを保ちます。反対に、お湯割りも冷めにくい。ちなみに冷蔵庫で冷やしておくと、より一層冷たさをキープできるのでおすすめ。その際冷凍庫はお避けください。ぬるくならないというのは、ゆっくりお酒を楽しむ人にとってはささやかに嬉しいことなのです。鏡面をきれいに保とうと気を使いがちですが、傷を恐れなくてもいいかなと個人的には思っています。使ううちに刻まれていく傷は、永く一緒に過ごしている「自分だけの」という証ですから。磨き屋シンジケート 二重タンブラー 8,800円唇で温度を楽しむグラスたち今まで缶ビールは350mlが入るグラスに全部注いで飲んでいましたが「コンパクト タンブラー 6oz」を家に迎えてからはスタイルが変わりました。缶から少しずつ注いで、クイッと飲む。一気に注ぐよりフレッシュな炭酸と温度を感じやすいのです。ジョッキではなく、瓶ビールで少しずつ飲むような楽しさもあります。そして、なんといってもキンキンの冷たさがガラス越しに唇に直撃するほどの薄さ。取り扱いにはちょっと気を使うものの、二重タンブラーとは違ったアプローチでビールを楽しめます。「ビールはちょっとで十分」という方にもおすすめのサイズ感。コンパクト タンブラー 1,870円唇で楽しむという点では、磨き屋シンジケートの「一口ビールタンブラー」も同様。こちらは金属だから薄いのに割れない、そして内面まで鏡面仕上げなので、長持ちするクリーミーな泡に仕上がるという嬉しい効果も。磨き屋シンジケート ビアタンブラー 4,400円熱伝導率という点で「銅」にかなう素材はそうありません。某珈琲店チェーンのアイスコーヒーマグも手掛ける新光金属の「ビアジョッキ リファインドマグ」は、これ以上無いほどのキンキンを味わえます。熱が伝わりやすい、ということは結露ができやすいということですが、持ち手と脚がついているおかげで、テーブルが濡れるのをなかなか防いでくれるのは目からウロコです。ビアジョッキ リファインドマグ 4,400円銅ほどではないものの、錫もまたキンキンを味わえる金属。くわえて、「お酒の味が変わる」と人気の素材です。ガラス製と比較してみると、確かに変わるな、と個人的にも感じました。日本酒だと特にわかりやすいのですが、具体的には雑味がなくなるような、角が取れたまろやかさが感じられます。これは普段のお酒もより美味しくなる優秀なアイテムで、当店ロングセラーの理由も納得です。ビアカップ 7,150円NAJIMIタンブラー 8,250円愛のあまり、ところどころご紹介に力が入りました。こうやって色々並べてみると、私がワインとビールばっかりこだわっている感じになってしまいました。いい感じに酔ってきたら、日本酒編、サワー編、焼酎編、ウイスキー編も出てくるかも知れません。ご期待ください。
スタッフのおすすめコラム
-

徹底比較、お弁当箱の素材ごとの長所と短所。
素材ごとの長所と短所、比べてみました。春は新しいことを始めるのにぴったりな季節。新生活を迎える方もそうでない方も、お弁当作りを初めてみたいと思っている方は多いのではないでしょうか。お弁当箱選びで気になるのが、素材。今回はプラスチック、ステンレス、木と異なる素材のお弁当箱3つを比較してみました。容量(ml)ごとのサイズ感が知りたい方は、こちらのコラムもご参考にしてみてくださいね。徹底比較、うるしの弁当箱の容量と選び方。左から、簡単に今回参加する選手たちのご紹介を。tak TIGHT FIT ランチボックス簡単にロックできて密閉性のある、プラスチック製。内フタにお箸も付いてきます。電子レンジ:◯ 食洗機:◯ 保温器:×工房アイザワ 角長ランチボックスシンプルな構造で洗いやすい、ステンレス製。2段サイズもあって子供から大人まで使えます。電子レンジ:× 食洗機:◯ 保温器:◯杉の木クラフト うるしの弁当箱 (大)杉の木にうるしを施した、職人による手作りの木製。木の香りでとにかくごはんが美味しい。電子レンジ:× 食洗機:× 保温器:×この3つをサイズ、密閉性、重さ、洗いやすさ、においのそれぞれで比べてみましょう。ところどころ主観が入っていますが、ご了承下さい。お弁当箱のサイズ比較まずはそれぞれのサイズを実感していただくべく、コンビニのお弁当をそれぞれに詰めてみました。自分だったら、普段これくらいのサイズのお弁当を買うかな?という感じで参考にしてくださいね。食べるのが好きな自分としては正直小さいなあと思わざるを得ないサイズです。詰めにくいので海苔と明太子は取り除きました。しかしコンビニのお弁当ってこんなに茶色ばっかりだったっけ。ちなみにそれぞれの容量は以下の通り。TIGHT FIT ランチボックス:500ml角長ランチボックス 1段:500ml角長ランチボックス 2段:1000mlうるしの弁当箱(大):630mlそれでは詰めていきましょう。TIGHT FIT ランチボックスTIGHT FIT ランチボックスは容量500ml。角の曲線が控えめなおかげか、ごはんをギュッと詰めやすい印象。結構詰め込むことができました。角長ランチボックス 1段角長ランチボックス 1段は「TIGHT FIT」と同じ容量500ml。本体とフタだけのシンプル構造だから、小ぶりに見えて意外と容量があります。おかずの詰め方を工夫したらもうちょっと入ったかな、という感じ。角長ランチボックス 2段角長ランチボックスには「2段」サイズもあります。単純に「1段」タイプを2つ重ねたシンプル構造。容量も倍の1000mlと、食いしん坊もなかなか満足な大きさです。詰めてみると、だいぶスペースが余りましたね。うるしの弁当箱 (大)うるしの弁当箱(大)は容量630ml。若干余裕を残しながら、ピッタリ詰められました。お弁当箱に大事な密閉性は?TIGHT FIT ランチボックス:◎水を入れて振ってもほぼ漏れてこない密閉性があり、カチッとロックする安心感もあります。ただ音が鳴っても反対側が固定されていない場合があるので、ロックされているかしっかり確認した方が良さそう。角長ランチボックス 1段:◯ロック機構のないシンプルなフタ構造ですが、シリコンパッキンが付いています。付属のゴムバンドでフタを固定すると、水を入れて傾けても漏れてきませんでした。ゴムバンドを緩めるとすぐ漏れてくるので過信は禁物ですが、お弁当箱としては十分でしょう。うるしの弁当箱(大):△フタを被せるだけなので、密閉性はあまりありません。水気の少ないおかずを詰めて、風呂敷等でしっかり巻くことをおすすめしています。重さはそこまで差がないどれかが特別重い!と感じるほど大きな差はありませんが、うるしの弁当箱は群を抜いて軽いですね。「見た目よりもだいぶ軽い!」と言われる方が多くいらっしゃいます。TIGHT FIT...
-

土鍋よりも手軽に鍋しよう。休みの食べもの Vol.4
いつの間にかセミの声が消え、つい最近まで「暑い暑い」と言っていたはずなのに、だんだん肌寒くなってきた今日この頃。寒さを吹き飛ばし、温まれる料理と言えばやっぱり鍋料理。 CRAFT STOREスタッフが休日に、いろんな料理をしてみる企画の4回目、今回はこれからの寒い季節に向けた、おすすめの鍋アイテムを集めてみました。 登場人物 こいぬまさん:料理が上手いせいで休日に撮影に呼び出されるデザイナー。 清水(筆者):休日に写真を撮って飲んで食べるデザイナー。 うどんすき鍋 まずご紹介したいのは、中尾アルミの「アルミ打出 うどんすき鍋」。プロ用調理器具で信頼の厚い中尾アルミらしい、しっかり厚いアルミ製。なのに片手でラクラク持てる重さ。華やかで食卓でも映えるアイテムです。 うどんすき鍋の特徴は、具材が沈みこまないように底が浅く開けていて、麺を取る時に汁が飛びにくいよう、縁部分が広く水平に設計されているところ。熱伝導に優れたアルミ製なので、熱ムラがなくサッと火が通るのもいいですね。 その名の通り「うどんすき」に使われることが多いうどんすき鍋ですが、今回は「魚介のトマトスープパスタすき」なんてものを作ってみました。 平らな形だから、中身が見やすくてすごい華やかだよね。 トマト系は鮮やかだから特にいいね。平らなフチのおかげで汁はねしづらいのも確かにって感じ。 軽くて丈夫でめちゃくちゃ扱いやすいから、サッと鍋ものつくるのに良い。土鍋より好きだな。 アルミ打出 うどんすき鍋 8,580円 キッチンから食卓に、KOKURYU そのまま調理ができて、保温性に優れた器、KAGETSUのKOKURYU。 萬古焼のKOKURYUはオリジナル配合された土で耐火成分の含有率が高く、そのまま火にかけてもOK。そしてそのまま食卓に運んで食べることができるのでとても楽ちんなのです。 調理した鍋のまま食べられるから、器に移したり洗い物の手間が減らせるね。 なんともありがたいのが保温性。食卓に運んだ時に冷めてしまっては意味がない。そんな時こそ「KOKURYU」の出番。独自の耐火技術と保温性が保たれる丁度いい厚みになっているので、火から降ろしてもしばらくは温かさが持続します。 器に移し替えるのが面倒な料理とか、ちょっとずつつまむように食べるのにいいよね。お酒のお供とか。 それはね、最高。もしかしたら呑んべえのための器かも知れない 実際、10分くらいでしょうか。ちょっと席を外して戻ってもまだ湯気が上がって温かかったのはちょっと驚きでした。あたたかいのはいいことです。 すごい気軽になんちゃって鍋ができる。サイズも1,2人にちょうどいいな。 そのまま火にかければまた温め直せるってのもいいね。お酒飲みながら、のこりの出汁でシメれるってのもまた最高。 KOKURYU 4,400円 pot...
-

3年目のうるしの弁当箱、修理に出しました。
CRAFT STOREの人気アイテムのひとつ、杉の木クラフトの「うるしの弁当箱」は修理が可能なことはご存知でしたか?うるしの弁当箱を愛用して3年目になるスタッフ タクミくんが、ついにお弁当箱を修理に出そうとしているとの情報をゲット。せっかくの機会なので、ご本人のお話も聞きながら修理の様子をお届けします。今回は杉の木クラフトさんの工房にお弁当箱を持っていって、実際に「うるしの弁当箱」をつくる工程も見せていただきました。以前のお弁当コラム以来で、約2年ぶりにタクミくんにインタビュー。今でも変わらず美味しそうなお弁当を食べる姿を目にします。≫ごはんが美味しくなる「杉の木」に感動!お弁当男子のプルコギ弁当ー うるしの弁当箱とは今年で3年目のお付き合いとのことですが、最初と比べて変化を感じるところはありますか?漆がはげてきて、色が黒くくすんできた感じがします。黒いふつふつができましたが、職人の溝口さんからは使用上問題はないとのことだったので、気にせず使ってました。あとは少し欠けがあったり傷が目立つようになりましたね。ー 今回は漆の塗り直しをお願いしたいとのことでしたが、漆が薄くなってくるにつれて変わったことはありましたか?使う面では特に気にしなかったのですが、強いて言えば香りですかね。漆と杉が相まった香りがなんとも心地よかったのですが、それが今ではだんだんと薄れてきたので少し物寂しさを感じてました。杉の香りに包まれた工房へタクミくんのお弁当箱には、ところどころ漆が薄くなって、表面が削れているような跡も。使い続けているからこそ見れる表情も味があって良いね〜!とみんなで盛り上がっていたところですが……修理をお願いすべく、さっそく福岡県糸島市にある杉の木クラフトへ!杉の木クラフトはのどかな自然に囲まれた場所にあります。いつもは青空が見渡せてとっても気持ち良いのですが、この日はくもりでした。修理のお話の前に、作業風景を少し覗かせていただけることに。いつも杉の木の香りがいっぱいで、ゆるりとラジオが流れている工房。なんだか時間がゆっくりと流れているような気持ちになります。うるしの弁当箱は、職人が手で木の状態を感じながら、ゆっくり丁寧に曲げて作られています。一度体験させていただいたことがあるのですが、これが本当に難しい!曲げるスピードや力加減を少し間違えると、木が割れてしまうんです。天然漆を塗る姿も。漆は湿度によって色や状態が変化するそうで、こちらも職人さんが長年培ってきた感覚での調整が必要。ひとつずつ丁寧に、職人の手で漆のコーティングが施されます。この他にも、乾かしたり形を整えたり、いくつもの工程が手仕事によって行われ、ようやくひとつの「うるしの弁当箱」が完成します。「こんなに大事にされてうまれてくるんだなぁ。」と、ちょっと感動してしまいました。▼杉の木クラフトの「うるしの弁当箱」シリーズうるしの弁当箱 6,160円うるしの弁当箱 (正方形) 6,160円うるしの弁当箱(子ども) 5,500円うるしの弁当箱 (二段) 10,450円使い方で変わる、お弁当箱の表情では、いよいよ本題に!まずは修理を依頼するタクミくんのお弁当箱を溝口さんに見ていただきました。手にとってじっくり観察された溝口さんは「使い方がとってもいいですね〜。」と、なんだか嬉しそうでした。今までもお客様のお弁当箱を修理していただいていましたが、どんな風に使われてきたかによって、お弁当箱の状態は全然違うそう。ー タクミくん、使い方がすごく良いとのことでしたが、うるしの弁当箱を使うときに気をつけていることはありますか?まさか使い方で褒められるとは思ってませんでした。一応使う時に気をつけていたのはやはり「すぐ洗う」ですね。食べかすが固まってカピカピになったり、油がついたままにしておいたりするのが嫌だったので、基本すぐ洗っていました。どうしてもすぐに洗えない場合は帰宅後すぐぬるま湯に30分〜1時間ぐらいつけて、食器より気持ち優しめに洗うようにしています。あと時間があったら、洗った後にベランダで乾かしていました。使っているとどうしても水気を吸った蓋が反ってしまって、本体との噛み合わせが悪くなっちゃうので。丁寧に使う、というより、育てるというイメージなんでしょうか。うるしの弁当箱は他の愛用スタッフはもちろん、これまでに修理をご依頼いただいたお客様も大切に使っている印象が強いアイテム。修理は約1ヶ月ほどお時間を頂いていますが(お弁当箱の状態によります)、「これからもお弁当箱使いたいので待ちます!」と言っていただくことばかりです。愛着というか、自分の子供のような感覚で愛用してくださっているのかもな、と感じています。お弁当箱が帰ってきましたタクミくんのお弁当箱は、漆を塗り直して1ヶ月ほどで戻ってきました。修理前と比べて見ると、漆が塗られたことによってしっかり濃い色に。削れた跡もすっかり見えなくなりました。使い込んでいたことが改めてわかるなぁ。使い込まれたお弁当箱に漆を塗ったので、新品とはまた違った表情に。表面もなめらかになったのではないでしょうか。ー 待ちに待った我が子(お弁当箱)との再会、どうですか?これからも使い続けられそうですね。水はけが良くなりました。最初のころと同じような感じになったのかな。うるしの弁当箱は、もちろんこれからも使っていこうと思っています。また修理をお願いして弁当箱として使い続けていくのもいいし、古くなったらお菓子の入れ物とかにも使うのもありかなと思ってます。「弁当箱の第二の人生」的な。確かに、お弁当箱以外の使い方もできそう。杉の木クラフトに伺うと、いつもコーヒーと一緒に、うるしの弁当箱に入った手作りクッキーでおもてなししていただくのですが、なんだか温かく迎えてくださっている感じがするので大好きです。タクミくんのお弁当箱は、これからも少しずつ表情を変えながら育っていくんですね。ここで最後に、生まれ変わったお弁当箱での最初のご飯を見せていただきました。うるしのお弁当箱に入ったタクミくんのお昼ごはん、今日も美味しそうです。杉の木クラフトの「うるしの弁当箱」、修理をご希望の際はお問合せフォームよりご相談ください。